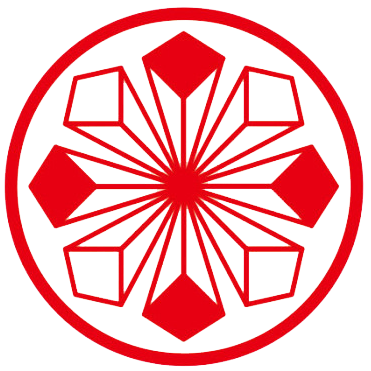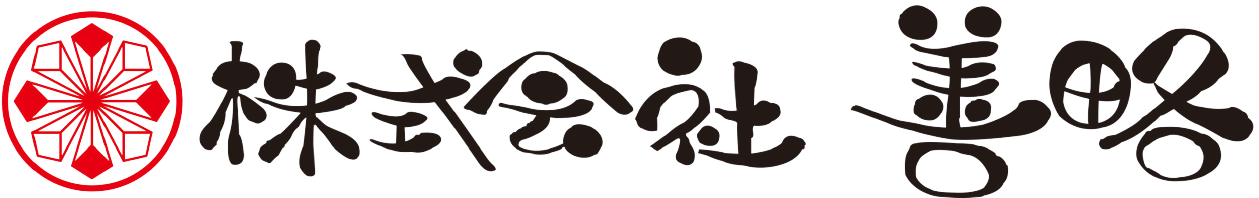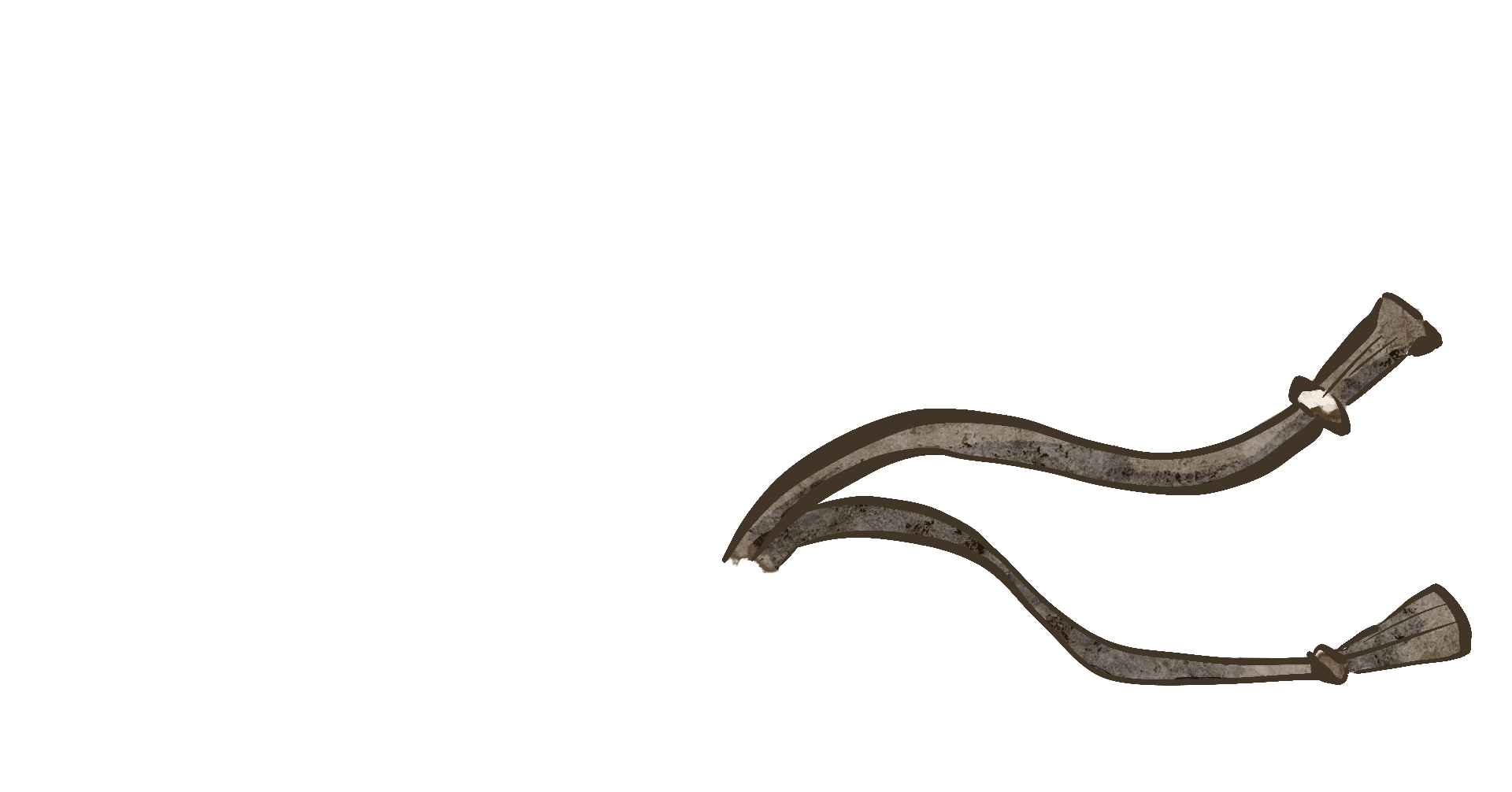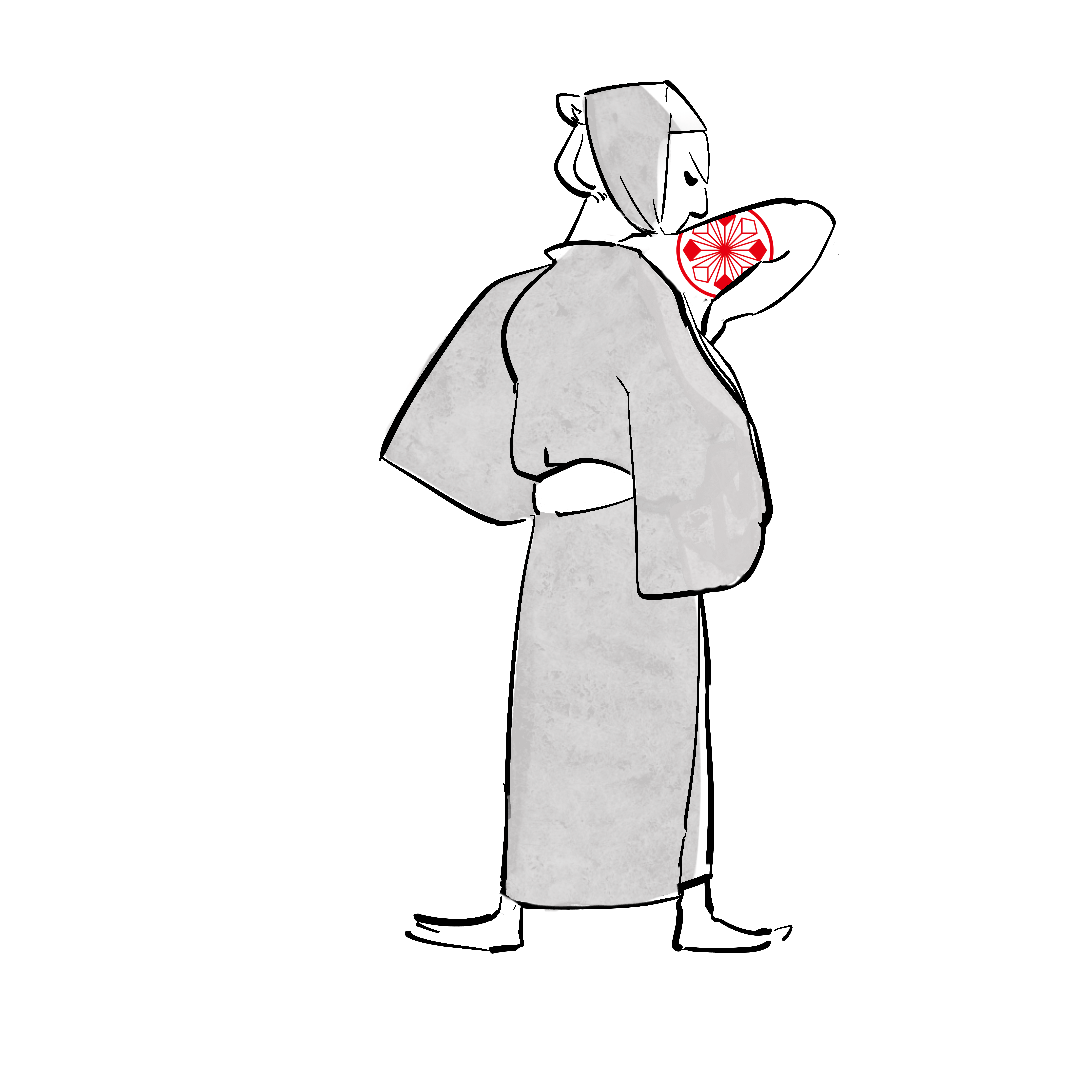このたび当コーナーにてリーダーシップに関するブログ記事を執筆させていただくことになりました庸介(ようすけ)です。
これまで私が、中小企業の経営支援の仕事に携わる中で感じたことがあります。経営者の多くは、自社商品・サービスの専門知識に自信を持っています。しかし、顧客や社内外スタッフ、サプライヤーなどとの関係においての「リーダーシップ」には、驚くほど自信を持てないことが多いのです。
それらへのヒントをイメージして、私なりのリーダーシップ論に関する考察を、いろいろな素材や切り口でお届けします。リーダーシップ論を身近に感じてもらえればうれしいです。以後、お見知りおきください。
初回は、2021年に放映されたNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公として、また2024年発行の新一万円札の顔として知られる渋沢栄一の話題です。
渋沢は幕末から明治期にかけて約500の事業会社を立ち上げた「近代日本経済の父」と称される人物です。
当時の日本は、不平等条約の改正を目指して経済力を強化する必要に迫られていました。その状況下で、渋沢は「株式会社」や「銀行」のシステムを普及させる重要な役割を果たしたのです。
そのリーダーシップは、「共有できる価値観で人々を巻き込み」「資金を集めて事業を興し」「社会に還元する」というものです。
渋沢の「リーダーシップ」とは、人を「引っ張る」イメージとは少々異なります。自身はオープンにビジョンを示し、人々がみずから納得して、あるべきところに投資する環境を整える。そうした、どちらかと言えば支援型のリーダーシップでした。
彼は、お札の発行を許可された民間銀行の一つとして、第一国立銀行(現在のみずほ銀行)を設立しました。しかし、自身の資産ではとても賄えません。そこで、各財閥や資産家に銀行の意義を説き、三井財閥などから多くの協力を得て、金融システムを構築しました。
集まった資金は新しい企業の設立につながり、社会全体に利益が還元されることとなります。
こうした渋沢の考えは、経済環境が不安定な現在においても示唆に富む、必要とされるリーダーの姿と言えるでしょう。
「お札の渋沢も笑ってる。」そう思えるように今の時代を生きる私たちも、渋沢のリーダーシップに倣い、正しい方向への努力をしたいところです。